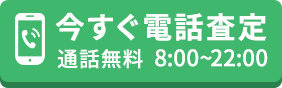ガソリン携行缶とは
ガソリン携行缶とはその名の通りガソリンを持ち運ぶための容器です。全国のカー用品店や、ホームセンターなどで、500mL~20Lまでの容器が販売されています。
素材は主に金属製であることが多く、プラスチック製の容器やガラス製の容器もありますが、素材の種類によって法律で定められた最大の容量が異なります。
- 金属容器:最大30L
- プラスチック容器・ガラス容器…最大10L
ガソリン携行缶を使う目的
自動車のガス欠を防止するのがガソリン携行缶を利用する主な目的です。 ガソリンスタンドの少ない場所を走行する際、初めて来た地域などでガソリンスタンドの位置を把握していない、災害が発生してガソリンスタンドが利用できないなど、ガソリンが枯渇してしまう様々なリスクを減らすことが可能になります。
ガス欠になってしまうと、自動車は一切動けなくなってしまいますので、JAFなどに依頼してガソリンを運んでもらうしかなくなります。 また、ガソリンは車の各機構の潤滑液や冷却にも利用されているため、ガス欠を繰り返すと、車のパーツを痛めて故障の原因になってしまいます。
それ以外の用途としては、公道を走行できない競技用車両に給油したり、発電機・農業機械・船などのエンジンを搭載するものへの給油に利用できます。
ガソリン携行缶を利用する際の注意点
ガソリンは危険物であるため、取扱いにあたって様々な注意点があります。
①本人確認や使用目的の確認が必要
令和元年12月20日に、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が交付され、ガソリンを購入する際は、本人確認や使用目的の確認が必要になりました。また、ガソリンを販売する全国のガソリンスタンドなどは、販売記録を作成することが義務付けられています。
②ガソリンは定められた容器以外に入れてはならない
消防法で定められた容器以外にはガソリンを入れることはできません。 日本ではプラスチック製の容器は10Lまでと定められていますが、国外ではプラスチック製でそれ以上の容量の容器があります。 国によってサイズの規定などは異なりますので、日本国内で販売されている容器を利用しましょう。
③ガソリン携行缶への給油はガソリンスタンドの従業員が行う必要がある
ガソリン携行缶への給油は、顧客がしてはならず、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があると法律で定められています。 例えセルフ式のガソリンスタンドでも同様に、顧客自らが給油することは違法行為にあたります。
④給油作業は火気のない水平な場所に携行缶を設置しておこなう
当然ですが給油の際はタバコなどの火気は厳禁です。 ガソリンが漏れてしまってはいけないので、水平な場所で給油を行います。 また、静電気による引火を防ぐため、携行缶は水気のある床や地面などに設置するのが望ましいです。 ガソリン携行缶自体が熱を持っているときは給油作業してはなりません。常温になるまで冷ました後で給油してもらいましょう。
⑤保管・運搬の際は直射日光や高温を避ける。
発火してしまう可能性を下げるため、直射日光には当てないようにして、高温になる環境では保管しないようにします。
⑥開栓の際はエア調整ネジで圧力を調整し、閉栓の際はしっかりと密栓する
ガソリンは気化しやすいため、携行缶の内部の圧力が上昇して、そのまま開栓するとガソリンが噴き出してしまい、非常に危険です。 開栓の際はエア調整ネジを使って携行缶内の圧力を下げてから作業するようにしましょう。 また、栓を閉じる際にもよく密栓しておかなければ気化したガソリンが漏れ出て爆発してしまう可能性があるので気をつけましょう。
⑦消耗品は定期的に交換する
気密性を高めるためにキャップやエア調整ネジに付いているパッキンは経年劣化してしまうため、ガソリンが漏れ出す可能性があります。 消耗品は定期的に交換するようにしましょう。
⑧ガソリンの劣化を防ぐため長期保管しない
ガソリンは使わないまま保管していると、徐々に劣化します。 劣化してしまったガソリンは車の故障の原因となります。 半年ほど保管したら携行缶内のガソリンを給油に使って、携行缶に再度新しいガソリンを入れるようにしましょう。
万が一、身体(衣服)に引火した時は?
身体(衣服)にガソリンが付着し、更に引火してしまった場合、どのように対処するのが有効がご存知ですか?
ガソリンは油(非水溶性)で水よりも比重が軽いため、ガソリンで燃えているところに水をかけても消火できないばかりか、油が飛散してより燃え広がってしまいます。 そのため、ガソリンでの火災は空気(酸素)の供給を遮断する「窒息消火」をする必要があります。 ガソリンの火災を消火するには二酸化炭素消化器・ハロゲン化消化器・機械泡消化器などが有効ですが、物に対してこれらの消火器を使用する場合は問題ないものの、人を消火する場合には酸素供給が完全に絶たれると炎が消えたとしても酸欠状態になってしまうため大変危険です。
では、身体(衣服)に着火した場合、どのように対処すれば良いでしょうか。
アメリカで火災予防の公衆教育プログラムの一環で考案されたもので、「ストップ・ドロップアンドロール」というものがあります。 アメリカでは身体(衣服)に引火した時の自己防衛策として、消防士が一般市民に対して指導しているそうです。
①ストップ(止まる)
パニックになって走り回ってしまうと、炎が空気を多く取り込んで、勢いが強くなってしまいます。 服に火が付いたら立ち止まり、走り回らないようにしましょう。
②ドロップ(倒れる)
立ったままでは消火されず、火は上向きに伸びますので頭部や気道が焼かれてしまいます。 すぐに地面に倒れこみましょう。
③ロール(転がる)
地面に倒れ込んだ後は、火を地面に押し付けるように転がりましょう。 地面に押し付けることで空気を取り込めなくなり、窒息消火させることができます。