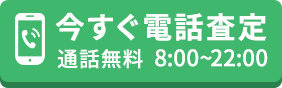タイヤの空気圧が低い場合
タイヤの空気圧が低い場合は、タイヤのたわみが大きくなり、走行中の振動などが伝わり難くなるので、乗り心地は良くなります。 ただし、空気圧が低いとタイヤが変形しやすくなるため、転がり抵抗の値も大きくなります。 その為、速度を出し辛くなり、速度を出すためにより多くアクセルを踏む必要があるため、燃費が悪化します。 空気圧が低いということは、タイヤがたるんでいるのでショルダー部(タイヤの接地するサイドの部分)がセンター部(タイヤの接地する中央部分)に比べて地面に強く接地し、ショルダー部の偏摩耗が発生してしまいます。 空気圧が低いと路面との接地面積が広くなり、雨や雪の天気の場合、スリップしやすくなってしまいます。 接地面積が広い方が雨や雪の際でもグリップ力が上がりそうな気がしますが、実はそうではありません。 雨や雪でスリップしてしまう原因は、雨や雪が膜のようになってタイヤが地面に直接当たっていないので、本来のグリップ力を発揮できなくなるためです。 接地面積が広いということは、単位面積当たりの荷重が少なくなるということですので、雨や雪を押しのけて地面に接地するための力も弱くなり、タイヤが浮きやすくなるのです。 雪上で、地面(雪面)に接する面積の広いスキー板が滑りやすく、面積の狭いストックが雪を貫通して地面に突き立つ(グリップを得られる)ということを思い浮かべれば、車のタイヤでも接地面積が広い方が雨・雪の際に滑りやすいということを理解し易いかと思います。 その他にも、空気圧が低い状態で走行を続けると、タイヤが波打ったような形状に変形したまま回転する(スタンディングウェーブ現象といいます)ため、徐々に振動が大きくなり、最終的にタイヤがバーストしてしまう可能性があがります。
タイヤの空気圧が高い場合
タイヤの空気圧が高い場合は、基本的に低い場合と逆の走行性能になります。 接地面積が狭くなることにより、雨や雪の際に(単位面積当たりの荷重が多くなるため、雨や雪を突き抜けて地面に接地しやすくなるので)スリップし難くなります。 また、転がり抵抗が小さくなるので、速度を出しやすくなり、燃費が向上します。 ただし、空気圧が高いタイヤは良いことばかりというわけでなく、悪いところ・危険なところも多く存在します。 まず、空気圧が高いことでタイヤが固く変形し辛くなるため、走行中の振動を拾いやすくなり、乗り心地が悪くなります。 また、タイヤのセンター部が盛り上がるため、センター部の偏摩耗が発生します。 そして、タイヤにかかる負荷(タイヤ内側から外側に出ようとする力)が大きくなるので、タイヤのバーストが発生しやすくなり、バーストした際の衝撃力も増加してしまいます。
適正な空気圧の場合
タイヤの空気圧は高くても、低くても危険なことがわかりました。 つまり、タイヤの空気圧はその中間である適正値に保つのが一番安全であるということです。 では、どの程度の空気圧が適正値なのでしょうか。 例え同じタイヤを利用するとしても、車両の重量・駆動方式・サスペンションなどにより適正空気圧は異なるため、全ての車に対して一括りに言えるものではありません。 その車両の適正空気圧を知るには、車両のドアヒンジの付近に貼り付けられたステッカーに記載されている空気圧を確認しましょう。 新車購入時は納車の直前に空気圧が適正に調整され、また1ヶ月検診・6ヶ月検診・12ヶ月検診・車検などの点検の際にも適正空気圧に調整して貰えるはずです。 しかし、タイヤの空気圧というのは、プロのレースドライバーが真っ先に確認する項目であると言われるくらい重要なものですので、工場で検査してもらう時だけでなく、自分でも定期的に空気圧を確認するのが望ましいでしょう。