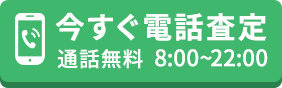デンマークの飲酒運転への罰則
日本で飲酒運転をした人(事故は無し)に対する罰則は、
| 罰則 | |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 違反点数35点 |
| 酒気帯び運転 呼気中アルコール量 0.15mg/L以上~0.25mg/L未満 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数25点 |
| 酒気帯び運転 呼気中アルコール量 0.25mg/L以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 違反点数13点 |
また、違反点数による罰則は、違反点数13点で免許停止90日、違反点数25点で免許取消+欠格期間2年、違反点数35点で免許取消+欠格期間3年、になります。
これに対し、デンマークの飲酒運転への罰則は厳しいだけでなく、印象的なものになっています。 デンマークでは飲酒運転で捕まった場合、目の前で愛車をレッカー車で没収され、没収した車はオークションにかけられ、その売上は国庫に入るようです。更に車の処分だけでなく、運転免許も取り消しとなり、最低でも月収1ヶ月分の罰金も課せられます。 デンマークで2014年から施行された、非常にインパクトがある「愛車をその場で没収」の効果もあってか、飲酒運転による死亡者数・重傷者数が約半数になるなど、改善が見られたそうです。
確かに罰則強化によって飲酒運転の違反者と、それによる被害者が減るのは確かなようで、日本でも2007年に道路交通法が改正されたものの、まだ罰則の見直しはあっても良いのではないかという意見もありますが、デンマークの方法だけでは根絶には至りませんでした。 罰則を強化した所で、「飲んだけどまだ酔ってないから大丈夫」「そんなに重い罰則を受けるような悪いことじゃない」「どうせバレないし問題ない」という考えで飲酒運転をする人や、普段は飲酒運転をする気がなくても何らかの原因により冷静さを失って突発的に飲酒運転してしまうケースなどもあるため、罰則による警告・抑止や、「一人一人が自覚しましょう」といった全てのドライバーの意識・良心に期待するだけでは、限界があるようです。
では、そうすれば更に減らせるのかと言えば、「人の意思が介在しないシステムで制御・抑制する」という方法です。
アルコールインターロック装置
呼気などから飲酒の有無を判断し、飲酒状態と判断された場合にはエンジンを始動しないようロックする装置を「アルコールインターロック装置」と言います。 飲酒運転を減らすことができる装置として既に一部では実用化されています。
「装置を取り外す」「運転者以外の飲酒していない人が代わりに吹き込む」といった不正・抜け道の問題もありますが、この装置の最大の問題は、「広く普及させるのが難しい」という所です。 「飲酒運転しない人にとっては無駄に費用が高くなるだけ」「飲酒運転する人にとっては邪魔な装置を付けたくない(費用もかかる)」ということで、自家用車に自主的に装置を付ける人はほぼいないでしょう。
装置の取り付けを義務化するしか普及させる方法はありませんが、十数万円かかる装置ですので、その負担は殆どの「飲酒運転をしない善良なドライバー」にとって重くのしかかります。 そのため、一般には普及しておらず、昨年時点で日本で「アルコールインターロック装置」を導入している車両は1600台程度で、ほとんどが運送業者です。(運送業は「アルコールインターロック装置」によって従業員の飲酒運転リスクの低減や、消費者の信頼獲得ができるなどのメリットがあります)
なお、欧米の一部の国・州において、飲酒運転したドライバーに対してアルコールインターロック装置の設置を義務化している所があります。 これは、一度目の飲酒運転こそ防げませんが、飲酒運転をしたドライバーだけが装置購入費用を負担する事になり、「飲酒運転をしない善良なドライバー」は何ら影響がないため、現実的な措置と言えます。 警視庁のデータによると、飲酒運転の検挙者は6割が再犯者であるため、飲酒運転をしたドライバーに対してアルコールインターロック装置設置義務化するだけでも、かなり大きな効果があると考えられます。
完全自動運転
ドライバーの操作を全く必要としなくなるレベルの自動運転(日本政府や米国運輸省道路交通安全局が定義するレベル4の自動運転)を「完全自動運転」と言いますが、完全自動運転を実現することができれば、ドライバー(登場者)は飲酒しても車を利用することが可能になります。
飲酒運転をしてしまう人の殆どは、「飲酒運転」そのものが「目的」で違反しているわけではないと考えられます。 「お酒を飲みたい」という目的と、「(自宅などに)移動したい」という「目的」がそれぞれ個別にあり、その2つが組み合わさった状況で飲酒後に「自動車を運転する」という「手段」を用いると、違反してしまうことになります。 つまり、「(自宅などに)移動したい」という「目的」が、「完全自動運転システムに任せる」という「手段」で達成できるのであれば、「お酒を飲みたい」と、「(自宅などに)移動したい」という両方の目的を飲酒運転せずに達成できるのです。
これは、今まで「車を運転しなければならないから、お酒は飲みたいけど我慢してノンアルコールのドリンクにしていたドライバー」にとって朗報であり、飲酒後に運転できなくするだけの「アルコールインターロック装置」とは違い、「飲酒運転をしない善良なドライバー」が積極的に導入する動機になり得ます。
ただし、自動運転技術はまだ発展途上のものであり、完全自動運転となると非常に時間がかかると思われ、また「アルコールインターロック装置」と同様にコスト面(=普及面)での問題があるでしょう。
まとめ
罰則や、ドライバーの意識に訴えかけるという事は重要ではありますが、それだけでは飲酒運転の根絶は難しいものですので、システムによる制御も必要になりますが、全ドライバーへの普及となるとコスト等の面で現時点では現実的ではありません。 「違反者にはアルコールインターロック装置の設置義務化」など現時点で対応可能な罰則の見直しをして、アルコールインターロック装置の低コスト化(ある程度低コスト化出来た段階で新車は設置義務化するなど)や、将来的には完全自動運転の普及を目指すなど、時間はかかりますが段階を追って対処していくのが現実的ではないしょうか。