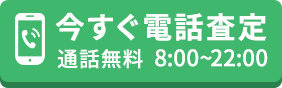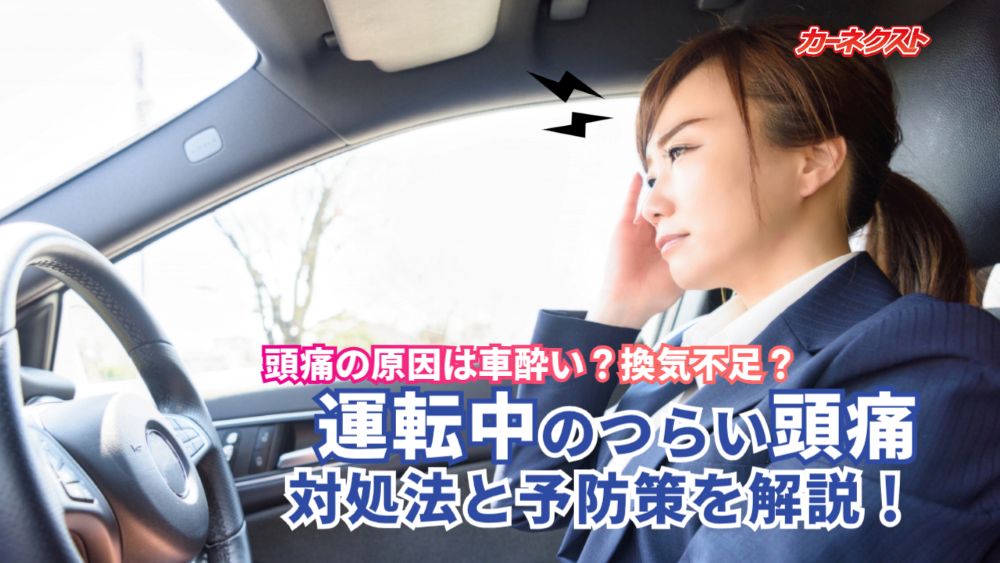頭痛は300以上の種類があり、原因や対処法もそれぞれ異なります。もしも運転中に頭痛が起こったら、痛みが気になって車の運転への集中力が欠如してしまう可能性もあり、最悪の場合大きな事故を起こしかねません。
こちらでは、運転中に頭痛が起こって辛くなったときの対処法や、運転中に頭痛が起こる原因とその予防策について解説します。
運転中に頭痛が起こる原因は

車の運転中に頭痛が起こった場合は、いくつかの原因が考えられます。車の運転中であることを起因とする頭痛と、原因となる疾患がない一次性頭痛がありますが、こちらでは車の運転中を起因とする頭痛の原因と予防方法について、詳しく解説します。
長時間運転で血流が悪くなった(ロングドライブ症候群)
長距離運転を行ったあとに頭痛やめまいが起こったり、吐き気や食欲不振になる症状のことをロングドライブ症候群といいます。長距離運転(ロングドライブ)のために体が長時間同じ体勢を取り続けた影響で、首や肩が異常な緊張状態となり、肩こりや首回りのむくみから頭痛が起こります。
特に高速道路で渋滞に巻き込まれたことによる長距離運転の場合、トイレ休憩が取りづらいため水分摂取を控えてしまったことでむくみが起こりやすくなったり、緊張状態が続いた上に脱水症状が重なってさらに血流が悪くなってしまうため、ロングドライブ症候群の症状がさらに悪化することがあります。
ロングドライブ症候群にならないための予防方法
前述の通りロングドライブ症候群は、長時間運転を同じ体勢で続けていると同時に水分もあまり取らないことで血流が滞り、肩こりやむくみが発生して頭痛につながります。このようなロングドライブ症候群にならないためには、こまめな休憩を取って体を動かすことと、水分補給をしっかりと行うことが大切です。水分は一気に取るのはなく、水か麦茶など利尿作用が控えめな飲みものを選び、コップ一杯(100~200cc)くらいの量をゆっくり飲むと良いでしょう。長距離移動になるとわかっている場合は、予め休憩場所を把握しておくことと、時間に余裕をもって運転をスタートすることで休憩も取りやすくなり、身体や精神的な負担を減らすことができます。
車酔いの症状による頭痛
車酔い(乗り物酔い)の症状の一つとして、頭痛が起こることがあります。車酔いは、乗り物の揺れや加速・減速による反復情報が耳(内耳)から、車外の変わっていく景色などの視覚情報は目から、乗車している車の揺れが直接身体からと、沢山の情報が入ってくることとそれぞれの内容がズレることで脳が混乱してしまい、自律神経の働きが乱れることで起こります。
車酔いになってしまうと段階的に症状が変わっていきますが、初期症状として生つば、あくび、頭が重い、頭痛などがあります。さらに症状が重くなると、吐き気や冷や汗、顔面蒼白、めまいが起こり、症状が悪化すると嘔吐してしまいます。
車酔いの症状を緩和するための予防方法
車酔い(乗り物酔い)は、自律神経の働きの乱れからと解説しましたが、その他にも嗅覚からの不快感、ストレス・不安、疲れや睡眠不足による体調不良等が要因になることもあります。
エアコンフィルターの汚れや食べかす等による車内の匂いも原因となり得ますので、フィルター掃除や車内の換気は適切に行いましょう。スマートフォンやゲーム機などを走行中の車内で使用すると視覚情報とのズレが、車酔いにつながることもあります。ゲームや読書等は控えて、できるだけ車の行き先をみるようにしましょう。
また、4歳から12歳くらいまでは脳の発達期のため車酔いになりやすく、子供のころに車酔いになった記憶からストレスを感じて、車酔いになってしまうこともあります。車に酔いやすい方は、予め市販の酔い止め薬等を服用しておくと、薬の効果だけでなく服用の安心感からストレスも緩和できるため、乗車が避けられない場面等では市販薬の活用もおすすめします。
車内換気が足りず二酸化炭素濃度が高い
車内温度を保つためや、花粉や黄砂などを車内に入れたくないといった理由から、車内換気をせずに閉じ切ったままにして運転することがあるかもしれません。実は、車内換気を怠ると空気中の二酸化炭素濃度が高くなり、酸素傷害が起こることで、呼吸困難や頭痛などの体調不良に陥ってしまうことがあるとご存知でしょうか。
車内の二酸化炭素濃度は目で見て確認することはできませんが、実は二人以上が乗車している状態で窓を閉めきり、内気循環モードで走行を始めると、急激に車内の二酸化炭素濃度が高くなります。この濃度が1,000ppm以上になると、酸素傷害が起こり眠気などの症状が現れます。さらに二酸化炭素濃度が2,000ppmを超えると頭痛や息苦しさを感じるようになり、運転への集中力が低下するといわれています。二酸化炭素濃度が5,000ppmを超えてしまうと、一日の職場暴露限度を超える(労働者が有害物質にさらされる量の制限基準を超える)ことと同等になり、酸素欠乏証などの危険がある数値まで上昇していますので、速やかに換気が必要です。
車内の二酸化炭素濃度を下げる方法
車内の室温のためにカーエアコンの内気循環モードを使用すると、二酸化炭素濃度が急激に上昇する原因となります。そのため、室温を上げるためにカーエアコンを利用するのであれば、外気導入モードを使用すると良いでしょう。また、夏場に気温が高くなった車内の温度を下げようと、乗車してすぐにエアコンを付けることもあると思いますが、その際も車内の暑い空気を一度ドアを開閉して換気し、エアコンをつけた状態で数分間窓を開けたまま走行すると空気が入れ替えられることで冷房の効きも速くなり、二酸化炭素濃度を下げることも同時にできます。

運転中に頭痛になった時の対処方法

運転中に頭痛が起こった時、軽度の痛みの場合もあれば、視界不良で目の前が見えづらくなったり、集中できなくなるような強い痛みで運転に支障が出る場合もあります。このような頭痛を緩和する方法はあるのでしょうか。
前項では車の運転を起因とする頭痛と、その予防策をご紹介しましたが、こちらでは他の病気が起因ではなく、原因がない一次性頭痛が起こった場合の対処法をご紹介します。一次性頭痛の【緊張型頭痛】【片頭痛】【群発頭痛】はそれぞれどのような対処が有効なのでしょうか。
車の運転中にひどい頭痛になってしまった時は、まずは運転中の車を安全な路肩等へ寄せて停車し、夜間時など視認性が悪い時は後続車に停車車両があることを伝えるため、必ずハザードランプを点灯させておきましょう。
緊張型頭痛はストレッチが有効
まず一つ目は緊張型頭痛です。緊張型頭痛は、身体的や精神的にストレスを感じていると起こる頭痛となっていて、頭が締め付けられるようなにぶい痛みがあり、肩こりや首筋のこり、眼精疲労を伴うことが多くなっています。
緊張型頭痛は長時間同じ体勢でいることで身体が強張って起こりやすいため、長時間続けて運転をする際は、こまめに休憩を取ってストレッチなどで血行を良くしたり、筋肉をほぐしてリラックスをすることが効果的です。また、体を温めることで血流が良くなり、痛みを和らげることができます。
片頭痛は前兆があった時に対処
二つ目の片頭痛は、頭の片側もしくは両側で、繰り返しズキンズキンと脈打つように痛みを感じる頭痛のことです。片頭痛の兆候が出てくると、光や音に敏感になります。運転中に対向車のヘッドライトや先行車のテールランプを直接見てしまったことでスイッチが入り、目の奥がチカチカして視界がぼやけ、片頭痛を引き起こす可能性があります。
片頭痛は緊張型頭痛と比べると痛みが強く、動くと痛みがひどくなることもあるため、日常生活に支障をきたす人も少なくありません。片頭痛は痛みのピーク時に市販の痛み止めを使用してもあまり効果がありません。また、繰り返し頭痛があるたびに服薬してしまうと、使用過多により薬が効かなくなる場合もあります。ズキンズキンとした強い痛みが毎月繰り返し起こっていて、痛み止めを長期間服用している場合は一度病院で相談されてみることをおすすめします。
群発頭痛は光を避けて休憩
群発頭痛は、一次性頭痛の中でも最も痛みが強く、一度発作が起こると約1~2か月程度続くといわれています。群発頭痛は目の奥が激しく痛み、痛みのある目と同じ側の鼻に涙や鼻水、鼻づまりなどが起こります。群発頭痛の発作が起こっている期間中に飲酒をすると、ほぼほぼ頭痛が起こると言われています。
群発頭痛の期間中に発作が起こると、痛みが強すぎて車の運転を続けることは難しいでしょう。安全なところへ車を移動できたら、市販の痛み止めでは効果がない場合も多いため、まずはその場で休憩を取りましょう。光が刺激になってしまい、群発頭痛の痛みのスイッチになることもあるため、太陽光や対向車のヘッドライトなどを直接見てしまわないように、昼夜問わずサングラスを着用されることをおすすめします。
まとめ
こちらの記事では、車の運転中に頭痛が起こる原因と、運転することには関わりがあるのか解説しました。車の運転を長距離や長時間行うと、同じ体勢で居続けることになるため身体が強張り、緊張状態が続くことで肩こりや首のこわばりから頭痛が起こる可能性があります。
また、比較的運転者ではなく同乗者に多いと思いますが、車酔い(乗り物酔い)になると、症状の一つとして頭痛が起こることがあります。乗り物酔いは体調不良や寝不足のほか、匂いや光の刺激にも影響を受けてしまうことがあります。早めに酔い止めを飲んだり、こまめな休憩を取ることで症状を緩和することもできるため、車での長距離移動を予定されている場合は、休憩スポットなどを事前に把握してから出発すると良いでしょう。