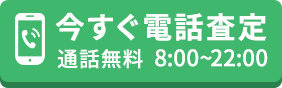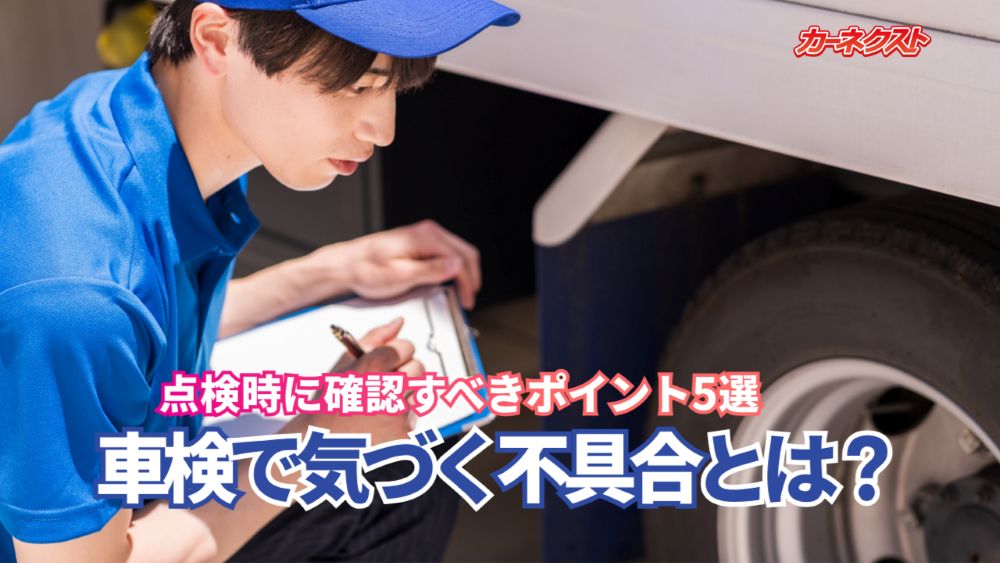自家用車は、新車購入から3年目とそれ以降は2年毎に車検を受ける必要があります。令和7年4月に道路運送車両法施行規則等が改正され、車検有効期間満了2ヵ月前に継続車検を受けることができるようになりました。車検切れのタイミングよりも前に継続車検を受けても、有効期限自体は車検が切れる予定日の翌日から2年間となるため、前もって受検をしても有効期限が短くなってしまう心配もなくなり、年度末の混雑を避けて事前に受検する方が増えています。
車検は「車が道路運送車両法の保安基準に適合しているかどうか」を点検する作業ですが、その点検時に思わぬ車の不具合が見つかって、未然に事故や大きな故障を防ぐことができたという事例があります。こちらでは、車検を受けた時に見つかることがある車の不具合ポイントについて詳しく解説します。
車検で点検する箇所

自家用車が車検を受けるには、ユーザー車検・車検専門店・ディーラー車検など様々な方法があります。車検を受けて保安基準に適合していると認められると、新しい車検証が発行されて継続して車に乗り続けることができます。まずは、車検で点検を受ける”保安基準に適合しているかどうか確認する箇所”について解説します。
車検とは
まず車検について解説します。車検の正式名称は「自動車検査登録制度」です。車検証に記載される(電子車検証の場合はデータに記録される)有効期間満了日より前の2ヵ月前から受検が可能となっており、車検(継続検査)を受けて保安基準の適合検査を合格することができれば、元々の車検有効期間が満了する日の翌日から次の車検有効期間満了日までを最新の有効期間とした新しい車検証が交付されます。
車検は、車を新規登録する時、もしくは継続使用する時に必要な点検で、受けることは法律によって定められた義務になります。検査対象自動車は、車検を受けて保安基準に適合していることが認められた上で、交付された自動車検査証を車載していなければ公道を走行してはならないと法律で定められているため、車検を受けていない状態で走行すると無車検運行として罰則が科されます。(刑事罰:6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、行政処分:違反点数6点加算、即免許停止)
車検の点検項目
車検で受ける点検項目は、外観や車体の同一性確認のほか、足回りや下回り等の部品点検もあります。点検項目を大きく分けると、下記9つの検査箇所となります。
| 点検項目 | 点検する内容 |
|---|---|
| 同一性の確認 | 車台番号、原動機型式、番号欄、種別、用途、車体の形状 |
| 外観検査 | 車枠・車体、保安装置、走行装置、乗車装置、灯火器類、原動機、電気装置、操縦装置 |
| サイドスリップ検査 | かじ取車輪横すべり量 |
| スピードメータ検査 | 速度計誤差 |
| ヘッドライト検査 | 照射光度、向き |
| ブレーキ検査 | 制動力測定 |
| 排気ガス検査 | 一酸化炭素、炭化水素 |
| 下回り検査(ピット方式) | かじ取り装置、緩衝装置、制御装置、原動機、動力伝達装置、車枠・車体、排気ガス発散防止装置、燃料装置、電気装置、走行装置 |
| 総合判定 | 書類審査と総合判定 |
同一性の確認は、車検証記載の情報を確認しながら、検査を受けている車台と同一かを照合する点検のことです。この同一性確認については、書面の情報に間違いがないか確認する点検ですので、不具合の発見につながることはほぼないでしょう。
次項で、車検点検時に実際に見つかる車の不具合とはどんなことがあるのかを解説します。
車検で不具合が見つかる?注意ポイント5選

車検の流れは、外観検査・内装検査、次に外周り検査・テスターによる検査をすると、前後のブレーキ検査・パーキング検査まで行い、次に排ガス検査を受けます。最後に下回り検査を受けて、すべての保安基準の適合が認められると、自動車検査票に修了ハンコが押され、新しい車検証の交付を受けることができます。
ユーザー車検となると、車検場に車を持ち込み、前述したような検査を受けて合否のみを確認することなりますので、合格が得られなければ再整備となりますが、点検内容に関係のない不具合については気づくことなく終わってしまうのですが、車検と整備を同時に行っているところで車検点検と整備を依頼したり、ユーザー車検の前に予備点検整備を受けておくと、車に不具合があったことや必要な部品交換に事前に気付くことができます。
内容としては、整備工場で部品交換をすることで解消できる軽微な不具合もありますが、オイル漏れなどの大きな事故に繋がる不具合が見つかることもあります。こちらでは車検を受ける前に、整備工場で点検・整備を受けていて見つかることの多い車の不具合について解説します。
タイヤ周りの違和感はブレーキの固着の可能性
タイヤの回転やグラつきをチェックする時に、タイヤの回転に違和感や負担がかかっているような重みがある場合、ブレーキの固着が起こっていることがあります。ブレーキの固着とは、ブレーキキャリパーがローターに外部から固着していることをいいます。ブレーキキャリパーが固着していると、ずっとブレーキを掛けたままの状態になるためブレーキ周りの部品は摩擦熱によって高温になります。摩擦熱で部品耐久が落ちるだけでなく、焦げたり発火したりする可能性があるため大変危険です。
金属が擦れるキーキーとした異音がある

下回り点検で異音がある時は、ブレーキパッドの減りが要因で金属音が鳴っている可能性があります。ブレーキの効きは車検の点検項目の一つで、点検内容としてはブレーキペダルを強く踏み込み、ブレーキの効きがあるかを確認します。ブレーキ装置の中でのブレーキパッドの役割は、ブレーキペダルを踏み込んだ際にパッド部分がディスクローターを挟み込むことで摩擦を発生させ、摩擦によって車を制止するように働きかけます。パッドが挟み込む時の接地面が削れてクッションを置かずにディスクローターを挟みこむことと傷がつく可能性があり、ディスクローターが傷ついて交換となると、ブレーキパッド交換費用と比べても、かなり高額になってしまう可能性があります。他の部品の劣化を防ぐためにも、ブレーキパッドは消耗品と考え、残量(厚さ)2~3mmとなった時には交換するようにしましょう。
冷却水漏れの不具合
現行のガソリンエンジン車のほとんどは水冷エンジンを採用しています。そのため、エンジンを冷やすために必要な冷却水が漏れて、足りていない状態で走行を続けるとエンジンが冷えず、オーバーヒートを起こして完全にエンジンが焼き付いて故障してしまい修理できない状況になることもあります。冷却水漏れは、甘い匂いの異臭がしたり、車体の下に色付きの水たまりや液漏れの跡ができる(冷却水はトラブルに気付けるように色付きで販売されている)ため、普段の日常点検時に見つかることもあります。大きなトラブルになる前に、冷却水の残量チェックを日常的に行いましょう。
オイル漏れの不具合
車の機関部分には、潤滑のためのオイルと圧力を生むためのオイルが使われています。特にエンジンやトランスミッションなどの運転中に常時動いている機関においては、部品の潤滑油が必須です。エンジンオイルが漏れていて枯渇してしまうと、潤滑油がない状態で動作しようとするため摩擦熱が発生し、高温でオーバーヒートを起こしたり、エンジン自体が焼きつく可能性があります。また、制動や操作に欠かせないブレーキ・ステアリングには、オイルが圧力を生むために使われています。オイルが枯渇すると、ブレーキを踏んでも制止力が弱かったり、パワーステアリングが利かずハンドルが重く操作しづらいといったトラブルが起こります。
エンジンオイルが漏れているとエンジン焼き付きの原因になったり、エンジンオイルが高温になると自然発火する可能性もあり、車両火災の危険も上がります。エンジンオイルの残量はオイルゲージがついていて目視確認しやすいため、日常点検を欠かさないようにしましょう。
バッテリーチェック
車検時にバッテリーで点検される内容は、「しっかりとバッテリーが固定されているかどうか」「木箱などの絶縁物によって覆われているかどうか」のみになっており、電圧等を図ることはありません。そのため、車検を通してすぐなのに、車のバッテリーが弱っていたため駐車中バッテリー上がりを起こした、ということも起こる可能性があります。バッテリーの寿命は2~5年と言われていますので、前回の車検以降交換をしていなかったという方は、車検を依頼する際に、併せてバッテリーの電圧を見てほしいと依頼しておいたり、交換をするか検討している旨を伝えて併せてみてもらうと良いでしょう。

まとめ
こちらの記事では、車検で点検を受ける時に初めて気づく可能性がある「車の不具合」について解説しました。車の不具合に早めに気づくことで、早期点検・整備ができるため、大きな故障や事故を避けることも可能になります。車検は年度末になると混みあい、行列ができることもあります。法改正によって、車検が切れる日の2ヵ月前から受検可能になりましたので、余裕を持った点検・整備を計画し、不具合に気付いた時点で速やかに対応できるようにしましょう。